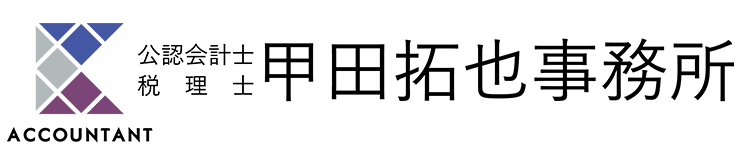初心者の確定申告には弥生会計がおすすめ!帳簿付けに申告書提出も
投稿日: , 更新日: , 年末調整・確定申告

確定申告を初めて行う方にとって「確定申告書の記入」と「帳簿付け」は不安に感じるところでしょう。その問題を解決してくれるのが弥生会計。帳簿付けから確定申告書の作成まで一貫してシステム上で行えます。本記事では確定申告の基礎知識と申告の流れ、初心者に弥生会計がおすすめな4つの理由について紹介します。
※記事は2021年11月現在の情報になります。
 |
サイト管理者の紹介
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表) 早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |
初めての方が知っておくべき確定申告の基礎知識
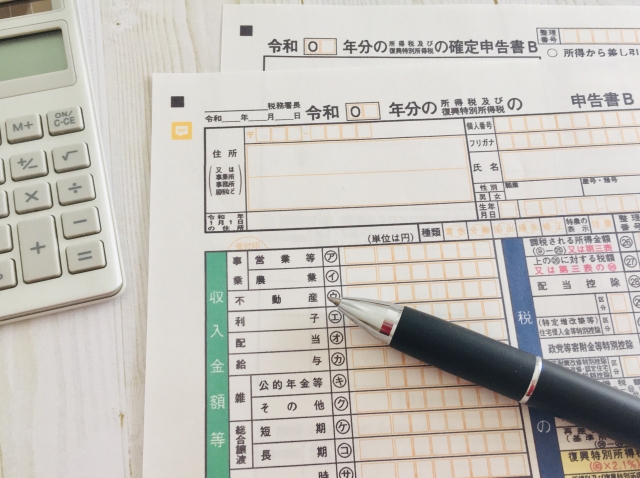
確定申告とは1年間の所得額を元に納税する税金額を計算すること。個人事業主の場合、1年間とは毎年1月1日から12月31日までを指しています。この期間の所得額や控除を税務署へ申告し、所得税を納税します。
確定申告では申告期間中に確定申告書と必要書類を税務署へ提出する必要があります。申告期間は原則的に翌年の2月16日から3月15日までです。(年によって変動あり)この間に書類の提出と納税を行う必要があります。
確定申告が必要な人
確定申告は基本的に1年のうちに何か収入を得たことのある人が行います。しかし、サラリーマンや公務員など会社で年末調整が実施される場合には自ら確定申告する必要はありません。
年末調整が実施された場合でも、会社の給与以外に所得がある人や自ら行うべき控除申請などがある人は別途確定申告する必要があります。
確定申告に必要な書類
確定申告にはこれらの書類が必要になります。
・確定申告書
・青色申告決算書または収支内訳書
・控除書類各種(ふるさと納税や生命保険料払込の証明書など)
・源泉徴収票(給与所得があった場合のみ)、支払調書(該当者のみ)
・本人確認書類
紙の確定申告書は国税庁のホームページやお近くの税務署などで入手できます。スマホやパソコンから確定申告することも可能です。
青色申告決算書または収支内訳書はどちらか一方のみの提出で構いません。青色申告を行う方は青色申告決算書を、白色申告を行う方は収支内訳書が必要になります。
控除書類と源泉徴収票は該当がある人のみの提出です。医療費控除や寄付金控除を利用される方は各種控除書類を、給与所得がある方は源泉徴収票を用意しましょう。
確定申告には青色申告と白色申告の2つがある
確定申告には青色申告と白色申告の2つがあります。青色申告を行うには、税務署に開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しなければなりません。そのため、これらの申請書を提出していない方は白色申告になります。
【青色申告と白色申告の特徴】
▼青色申告
・節税に有利な特別控除あり
・事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要
・経理処理が複雑
▼白色申告
・特別控除はなし
・事前に提出する書類はなし
・経理処理が簡単
白色申告は基本的にどなたでも利用可能です。サラリーマンや公務員の方のように、年末調整でほとんどの申告を終え控除のみ確定申告するようなケースでは白色申告で問題ありません。
一方、個人事業主やフリーランスの方のように、事業としての所得を申告する必要がある方は、青色申告を利用した方がお得でしょう。
確定申告の基本的な流れを把握しよう

ここからは確定申告の基本的な流れを順番にみていきましょう。確定申告は毎年3月15日が期限となっていますが、期限間際になってから作業を開始しては期限に間に合わない可能性があります。
確定申告の流れを把握し、余裕を持って申告が終えられるようスケジューリングしましょう。
帳簿を付ける
日々の取引を仕訳にし帳簿を作成します。売上や経費など計上漏れがないようこまめに処理を行いましょう。帳簿付けを行った金額は確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書を作成する際に使用します。
帳簿付けは確定申告前にまとめて行わず、週ごとや月ごとなど定期的に実施することをおすすめします。古いレシートや領収書などの紛失や内容を忘れないようにするためです。
青色申告の方は複式簿記にて帳簿付けを行います。白色申告の方は複式簿記より処理が簡単な単式簿記にて帳簿付けが可能です。複式簿記は会社の経理が行うレベルの処理が求められ、一方の単式簿記は家計簿レベルの帳簿付けで済みます。
必要書類を揃える
次に必要書類を揃えていきます。控除書類や源泉徴収票など確定申告に必要な書類を集めてください。
生命保険料や社会保険料の控除書類は毎年秋~冬にかけてご自宅に郵送されます。失くさないように保存しましょう。
確定申告書を作成する
帳簿と書類が揃ったら確定申告書を作成しましょう。基本的に確定申告書は帳簿や必要書類から記載すべき数値や情報を転記することで完成します。
確定申告書の書き方がわからない場合は税務署へ相談をしたり、各地の税務署などに設置される確定申告会場にて記入を手伝ってもらったりしましょう。
パソコンやスマホで確定申告をしたい方は確定申告書等作成コーナーを利用できます。また、税理士に依頼をしたり、クラウド会計ソフトを利用したりして確定申告する方法もあります。
作成した書類を提出する
確定申告書が完成したら、付属書類を添付して税務署へ提出しましょう。提出は税務署への持ち込みや郵送にて可能です。確定申告書等作成コーナーやクラウド会計ソフトを利用して確定申告を行う方はインターネット上にて確定申告書の提出ができます。
納税する(還付金が振り込まれる)
確定申告にて算出された納税額を期日までに振り込みましょう。還付になった場合は、確定申告の際に指定した口座に後日還付金が振り込まれます。
初心者の確定申告には弥生会計がおすすめ
弥生会計とは連続22年売上実績No.1 を誇る会計ソフトのことです。仕訳入力や帳簿の作成が簡単にできます。
弥生会計にはインターネット上で利用できるクラウド会計ソフトとパソコンにダウンロードして使う会計ソフトの2種類があります。初心者の方には「やよいの白色申告オンライン」「やよいの青色申告オンライン」と呼ばれるクラウド会計ソフトがおすすめです。
【弥生会計が向いている方】
・初めて確定申告する方
・簿記がよくわからない方
・初めて青色申告する方
・作業時間を減らしたい方
・電子申告を利用したい方
このような方は弥生会計を利用することで確定申告の不安を解決できる可能性が高いでしょう。
弥生会計が初心者の確定申告におすすめな4つの理由

初めて確定申告をしようとすると、これらのことで迷ってしまいますよね。
「帳簿ってどうやって付けるの?」
「確定申告書のどこに何を記入するの?」
この悩みを解決してくれるのが弥生会計です。弥生会計は帳簿付けがほぼ自動的にできるため簿記知識がない確定申告初心者にも優しい設計になっています。
また、帳簿付けから確定申告書の作成までシステム上で一貫してサポートしてくれるため、初心者の方でも簡単に確定申告書の作成が可能です。
簿記知識がなくても帳簿付けができる
簿記の知識がない方でも帳簿付けが簡単にできるところが弥生会計の特徴です。銀行明細やレシートのスキャナ画像を読み込み、日付や金額などを入力するだけで簡単に帳簿付けができます。青色申告の方には複式簿記の帳簿が自動作成されます。
取引データの自動取り込みで作業時間が削減できる
弥生会計はさまざまな会計データの読み込みが可能です。銀行明細、クレジットカードの取引データ、レシート、領収書などのデータを使い、自動的に帳簿付けができるようになっています。
従来はこれらのデータを見ながら手打ちで会計ソフトに入力していました。データの取り込み機能を活用すればこの入力作業にかかる時間を削減できます。
確定申告書類を自動作成できる
弥生会計では確定申告に必要なこれらの書類の作成も可能です。システムの案内に従って必要事項を入力すれば、これらの資料を簡単に作れます。
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
また、弥生会計から直接e-Taxにて確定申告の電子申告ができる機能も搭載しています。自宅で確定申告書の作成~提出まで終わらせたい方におすすめの機能です。
1年間無料でお試しができる
弥生会計には1年間のお試し期間が用意されています。ほぼすべての機能を1年間無料で利用でき、かつ最大2か月間は電話やメールでの初期サポートも利用可能です。いろいろな会計ソフトを比較の上導入するソフトを決めたい方はぜひ試しに利用してみましょう。
まとめ

確定申告では1年間の所得額を申告し納税額を計算します。所得があるほとんどの方が対象です。
確定申告は下記の流れで作業を進めます。
1.帳簿を付ける
2.必要書類を揃える
3.確定申告書を作成する
4.作成した書類を提出する
5.納税する・還付金が振り込まれる
初心者の方が確定申告を行う上で悩んでしまうのは「帳簿を付ける」「確定申告書を作成する」という作業です。この悩みを弥生会計は解決してくれます。
弥生会計を利用すると簿記知識のない方も帳簿付けを簡単に終えられます。また、確定申告書の作成もシステム上で完了します。
今回初めて確定申告をする、白色申告から青色申告に切り替え青色申告決算書の作成が必要な方などはぜひ弥生会計を試してみてください。
TOPに戻る