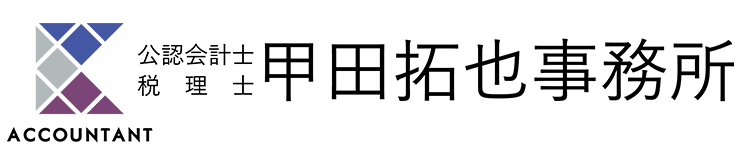電子帳簿保存法の改正で見積書の保存はどうなる?電子データでの保存要件を解説
投稿日: , 更新日: , 経費・勘定
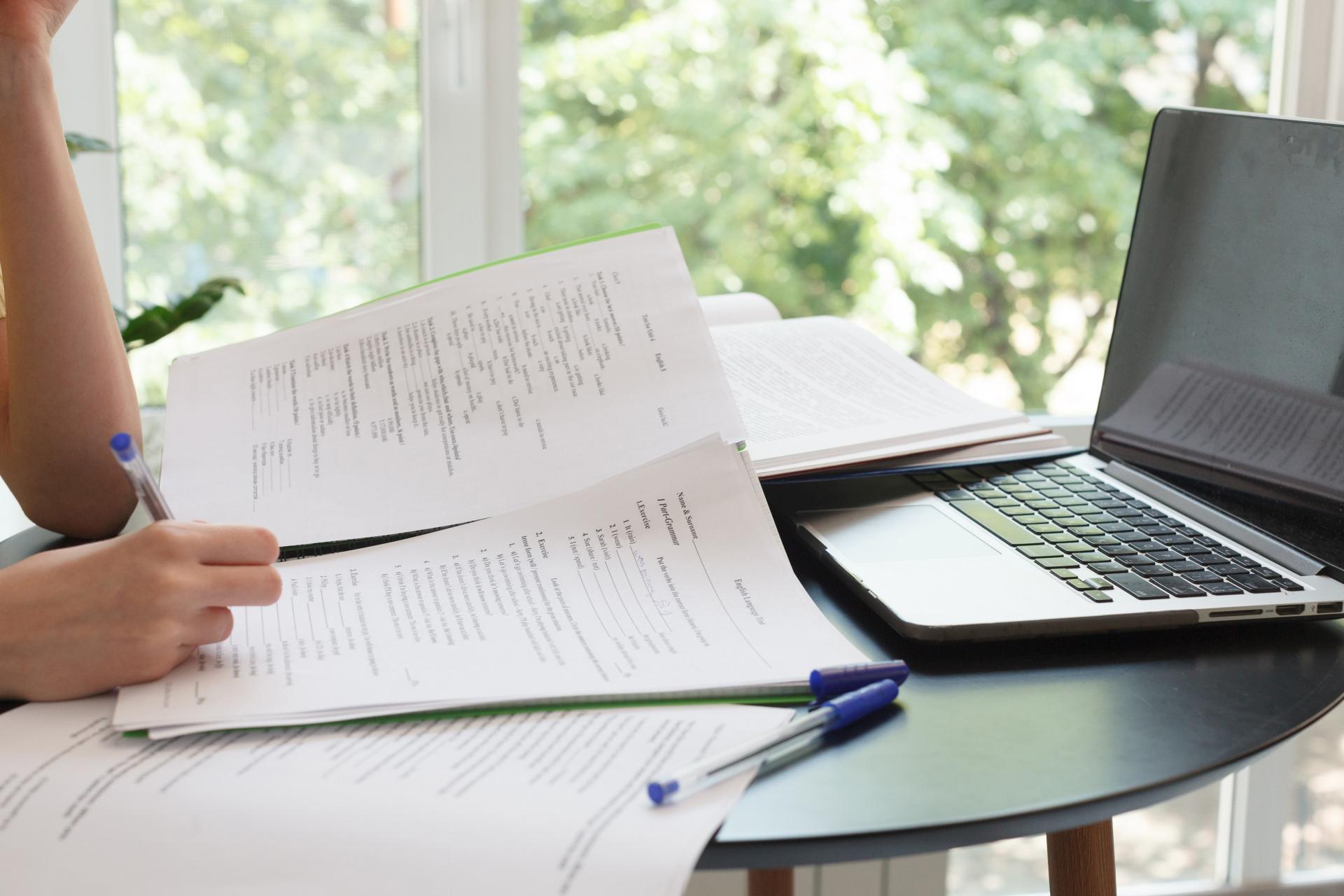
国税帳簿書類を対象にした電子帳簿保存法は改正されており、2024年1月1日からは原則として電子データで受け取った取引書類は印刷して保管できなくなります。
では、取引のなかで重要な位置を占める「見積書」について、最新の電子帳簿保存法ではどのような保存が必要になるのでしょうか。
本記事では2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法の内容と、見積書の保存方法の概要や要件などについて解説します。
電子帳簿保存法とは
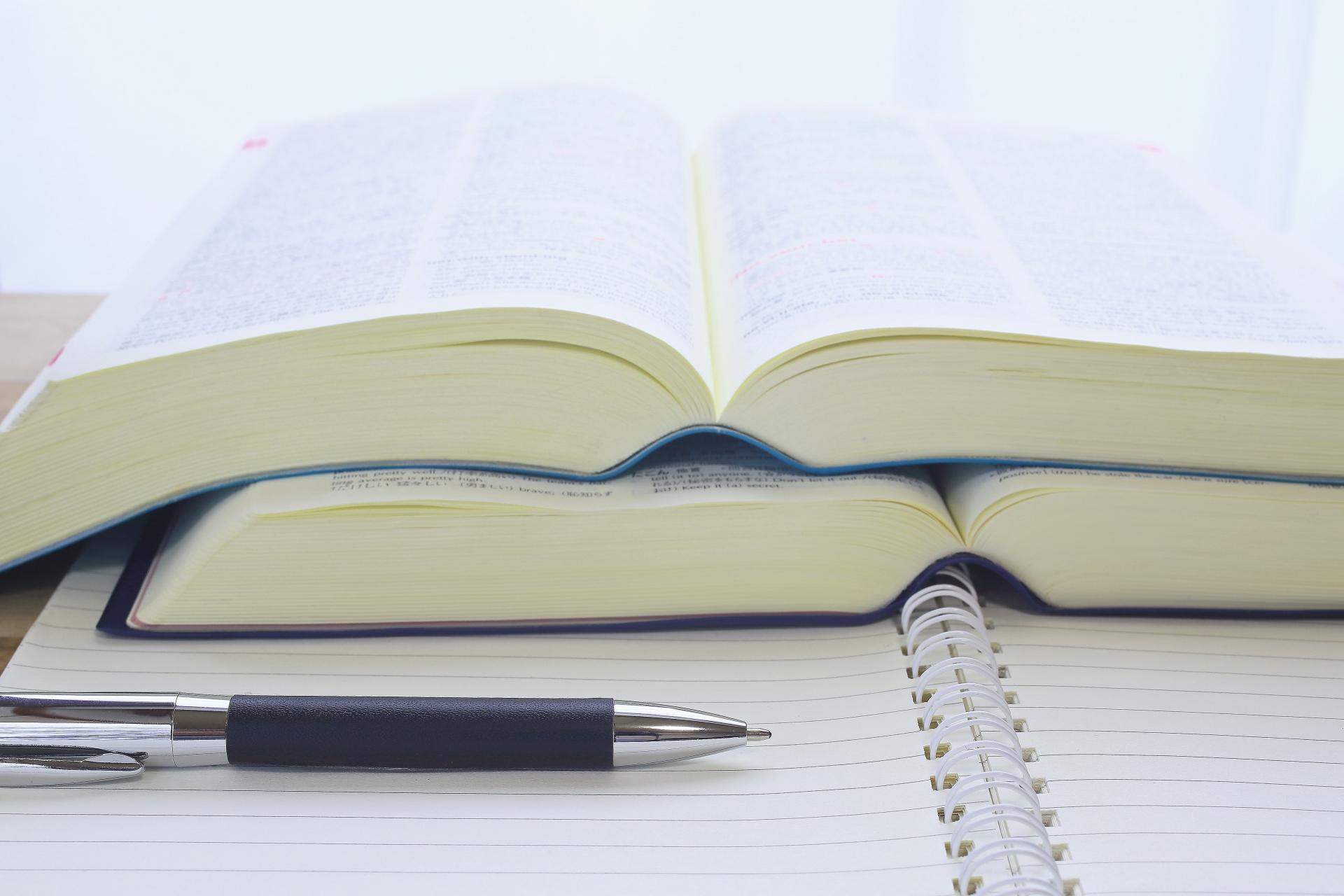
電子帳簿保存法は、紙で保存が義務付けられていた「国税関係帳簿」「国税関係書類」「取引関係書類」について、一定条件を満たすことを条件に電子データによる保存を認める法律です。
国税関係書類は5~7年間の保存が義務付けられており、書類の保管場所の確保や管理の人件費などの課題がありました。
2022年1月に改正されてからは電子取引データの紙保存ができなくなるなど、時代に即した法令に改正されています。同時に「適正課税」という観点から一部罰則の強化も行われており、法令の範囲内で適正な電子データ保管をする必要があります。
電子帳簿保存法で理解しておきたい3つの区分
電子帳簿保存法の概要を知るには、以下の3つの区分の違いを知ることが重要です。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引
電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、「電子帳簿保存法」と言葉が似ていますが、別の内容を指している点に注意が必要です。
電子帳簿等保存は、パソコンなどのコンピューターで電子的に作成した「国税関係書類」の電子保存を認めるものです。
会計ソフトなどパソコンで作成した「国税関係書類」「国税関係帳簿」「自己発行の取引関係書類」について、一定要件を満たすと電子データで保存できます。
スキャナ保存
スキャナ保存は文字通り、自社で作成した紙の書類の控えや先方から受け取った取引書類などを、一定の要件のもとでスキャンして電子データとしての保存を可能にするものです。
スキャナでのスキャンをイメージできますが、ほかにスマートフォンやデジタルカメラでの撮影による保存も同様です。
電子取引
注文書や契約書、見積書などの取引情報を紙ベースではなく、電子データで取引をおこなった場合の電子保存について定めたものです。
今回紹介する見積書も電子取引する場合はこの項目に該当し、一定要件を満たしたうえでの電子保存がすでに義務化されています。
2022年1月で改正された際の変更点

ここでは2022年1月の法改正で何が変わったのか、法改正の要点を紹介します。なかには任意ではなく義務になったものがあり、すでに宥恕期間も終了しています。
法令違反に該当しないよう、法改正の内容を十分に理解しておきましょう。
事前承認制度の廃止
改正前の電子帳簿保存法は特例の制度であることから、改正までは税務署に申告して税務署長の承認を得る必要がありました。事前承認制度は準備に数か月を要することもあるなど負担が大きなもので、電子帳簿保存法への適応に時間がかかるという問題がありました。
改正後の現在では国税関係帳簿・書類などのスキャナ保存に関して事前の申請と承認が不要になっています。
タイムスタンプ要件や適正事務処理要件の緩和
スキャナで国税関係のデータを保存するには、取引にデータ改ざんがないことを示すための「タイムスタンプ」の付与が必要です。
改正前は3日以内の付与が必要で事務的な負担が大きなものでしたが、改正後は「取引情報の修正・削除の履歴が残るシステム」「取引情報の修正・削除ができないシステム」を利用している場合などの条件を満たすことで、スタンプ付与の期間が最長2か月と7日になって事務負担が軽減されています。
また、改正以前はスキャナ保存時の不正を防止する観点から「社内既定の整備」「2名以上でのチェック」などの適正事務処理要件が存在しましたが、改正後は廃止されました、ただし、改ざんができないクラウドサービスやシステムを利用することが前提です。
検索要件の緩和
改正前はスキャンデータや電子取引データを電子保存する際、検索のための要件が多数あり、複数条件を組み合わせた検索ができることも必要でした。
改正後は検索要件について「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つに緩和されています。
ただし、「電子帳簿」に関しては、優良帳簿を満たす場合に以前と同様に複数の検索要件を満たす必要があります。
電子取引データの書面保存の廃止
以前は電子取引データを紙に保存しての保存が可能でしたが、改正後は認められなくなりました。
電子取引は電子的にやりとりをおこなった取引のことで、メールやクラウドサービスなどインターネットを介した取引だけでなく、電子データの保存媒体に保存して対面や郵送でやりとりした場合も含まれます。
【電子取引に該当する例】
|
電子取引データに関しては、電子のままで保存することがすべての事業者の義務になっています。
改正電子帳簿保存法で見積書の対応はどう変わった?

2022年1月からの改正電子帳簿保存法が施行されたことで、国税関係書類や取引書類の保存要件は大きく変わっています。
では、取引関係書類のなかでも「見積書」の扱いはどのように変わったのでしょうか。
ここでは改正電子帳簿保存法が適用された現在の見積書の保存要件について解説します。
改正電子帳簿保存法では保存義務が生じる
まず、見積書自体は保存義務があります。
法人税法によれば、取引に関して作成した書類や受領した書類について保存義務が定められています。
電子帳簿保存法では電子データでの保存義務は従来ありませんでしたが、改正後は電子取引データに関しては保存義務が定められました。
この「電子取引データ」には見積書も含まれます。
電子データで受け取った見積書や送信した見積書の控えは、電子的な保存が必要です。
見積書の保存要件
見積書を電子データで保存する場合、電子帳簿保存法の検索要件を満たすことが必要です。
取引年月日や取引金額、取引先で検索ができるようにしなければいけません。
紙でやりとりした見積書をスキャンする場合は2か月と7日以内にタイムスタンプを発行するか、データ訂正の記録が残るシステムなどを使っての保存も必要です。
見積書をはじめとした電子取引データの保存要件をまとめると以下のようになります。
| システム概要に関する書類の備え付け | 自社開発のプログラムを使って保存する場合、システムに関連したデータの作成方法や閲覧方法のマニュアルなどを記した「概要書」を備え付ける |
| 見読可能装置の備え付け | パソコンのディスプレイ・プリンタなどを設置して、電子データで保存した書類を画面で確認・出力できるようにする |
| 検索機能の確保 | 電子データで保存した書類は、取引年月日と取引金額、取引先で検索できる必要がある |
| データの真実性を担保する措置 | 「タイムスタンプの付与」「データの訂正や改ざんが記録されるシステムを付与」「改ざん防止に関する義務処理規定の整備・運用」などの条件を満たして電子データを保存する |
紙媒体と電子データが混在する場合の対応
見積書の紙の原本と電子データが混在している場合、紙の原本は紙のまま保存しておいて問題ありません。スキャナを利用して電子的に保存することもできます。
電子データの部分は電子データのみの見積書と同様に、タイムスタンプなど不正防止のシステムを付与したうえで「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにする必要があります。
電子帳簿保存法と見積書に関してよくある質問

最後に、電子帳簿保存法と見積書に関して、よくある質問と回答をまとめました。見積書の電子保存について気になることがある方は、読み進めてみてください。
契約に至らなかった見積書は保存が必要?
電子帳簿保存法では契約に至らなかった見積書の保存については明確に書かれていません。
ただ、保存をしない場合、「契約に至らなかった」ということを証明する手段がないことも事実です。
よって、作成した見積書については契約に至ったか、至らなかったかに関係なく、すべて保存しておいた方が良いでしょう。
見積書の保存期間は?
法人税法によれば、帳簿や取引で作成した書類は確定申告の提出期限の翌日から7年の保存が義務づけられています(青色申告書を提出した事業年度で欠損が生じたときなどは10年)。
また、個人事業主の場合でも5年間は見積書の保存が必要です。
電子データでの保存義務とは別に、紙の見積書であっても一定期間は保存する義務が生じます。
手書きによるPDFや郵送で見積書が届いたらどうする?
改正電子帳簿保存法ですべての事業者の義務になったのは、電子取引データの電子保存です。
PDFで送付された見積書についても、以下の要件を満たしたうえで電子保存が必要です。紙に出力しての保存は認められない点に注意が必要です。
- タイムスタンプ付与などの改ざん防止措置
- 日付、金額、取引先の検索設定
- ディスプレイやプリンタなど出力機器の備付け
一方、郵送などで紙の見積書が送付された場合に関しては、電子データで保存する必要はありません。紙を原本のまま保存することも、スキャナ保存することも可能です。
まとめ
現在の企業の営業活動において、見積書はPDFにしてメール添付するなど、電子データでやりとりすることが多いはずです。電子取引データの見積書は電子データのまま保存することが法律で義務付けられているので、保存要件を満たしたうえで電子保存をしましょう。
電子保存には自社開発のほか、クラウドサービスを利用することも可能です。書類管理業務の負担軽減のためにも、見積書などを電子データ保存で一本化できるよう、業務効率化を検討していきましょう。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |