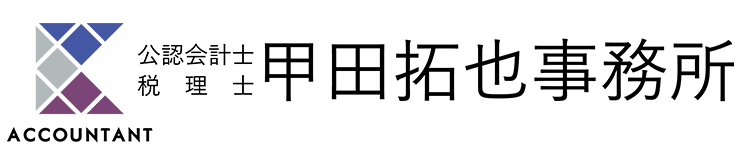電子帳簿保存法で新たに定められた「猶予期間(猶予措置)」とは? 従来の宥恕(ゆうじょ)措置との違いを解説
投稿日: , 更新日: , 経費・勘定
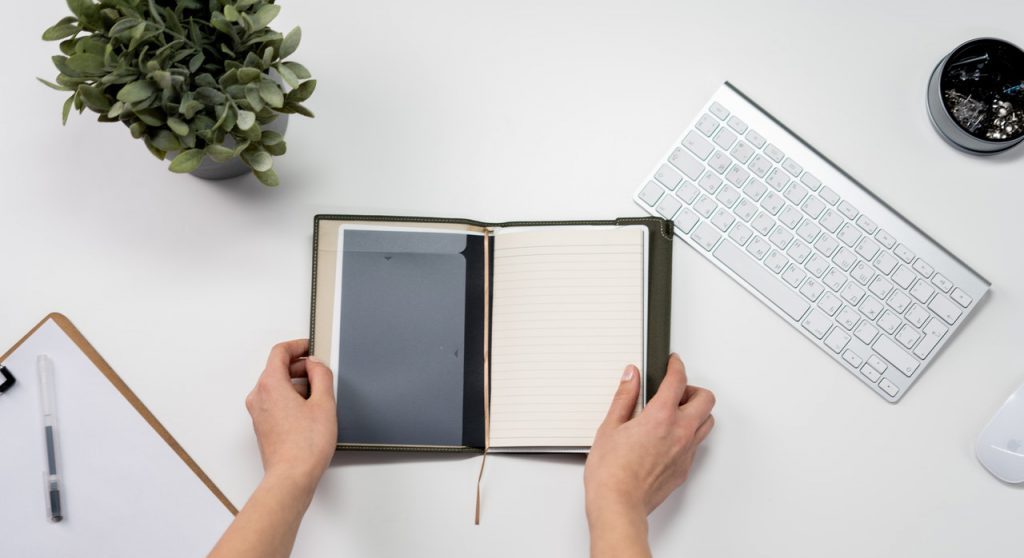
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子取引データの電子保存の義務化に関して2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が認められました。しかし、2024年になった現在では終了しています。
その代わり、2024年からは新たに期間を定めない猶予措置が設けられました。ただし、宥恕機関と全く同じ対応ではないため、事業者はそれぞれの違いを知っておくことが必要です。
本記事では2023年まで続いた宥恕措置と、2024年から新たにスタートした「猶予措置」について、各制度の概要や違いについて解説します。
電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、税法などで保管が必須の国税関係帳簿や国税関係書類について、紙ではなく電子データでの保管を可能にする法律のことです。
電子帳簿保存法の保存区分は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ」の3つに分かれています。
電子帳簿等保存では、システムで作成した帳簿や国税関係の書類について、プリントアウトせずに電子データのままで保存できます。一定範囲の帳簿が「優良な電子帳簿」として認められれば、後で対象の電子帳簿に過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減されます。
スキャナ保存は、紙で受領した請求書や領収書に関してスキャニングで保存することを認める区分です。スキャナだけでなく、要件さえ満たせばスマートフォンやデジタルカメラでも保存できます。
「電子取引データ保存」は、見積もり書や注文書、領収書などの取引書類について、電子データでやりとりした場合は、電子データで保存しなければいけないという義務規定です。
特に企業や個人事業主が対応を迫られているのは、義務化されている電子取引データの保存です。
電子帳簿保存法は2022年1月に法改正が実施されている

2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されました。主な改正点は以下のとおりです。
|
なかでも大きな改正といえるのが、電子取引データを電子情報で保管することの義務化です。
本改正によって電子取引データの紙での保存が原則禁止になり、電子取引で授受した取引情報は電子データのまま保管する必要があります。
しかし、準備期間の不足から対応が遅れる企業が続出したこともあり、2023年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)期間」が設けられました。
2023年12月まで適用されていた宥恕(ゆうじょ)措置とは
宥恕(ゆうじょ)措置とは、令和4年度税制改正大綱で定められた「経過措置」のことです。
宥恕措置では2022年1月1日から2023年12月31日の2年間にかけて、電子保存の要件を満たせない「やむを得ない事情」がある場合に限って、従来通りの紙保存が認められました。
電子保存の要件を満たせない企業が多かったことから、それらに配慮する形になっています。
やむを得ない事情とは、電子帳簿保存法に対応したシステムが整備されていなかったり、社内のワークフローが未整備だったりすることが該当します。これらに当てはまる場合に「やむを得ない事情」と判断される場合がありました。
この宥恕期間は2023年12月31日までの措置であり、2024年現在はすでに終了しています。
電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間は終了し、新たに「猶予期間」が始まっている

前述したとおり、電子取引の保存義務に関して設けられていた「宥恕(ゆうじょ)期間」が2023年12月31日で終了になっています。
一方、令和6年(2024年)の1月1日に改正電子帳簿保存法が新たに改正されており、2024年以降の法改正にまた変化が生じています。
2024年の法改正で新たに加わった電子帳簿保存法の「猶予措置」とは
2023年12月31日で終了した宥恕(ゆうじょ)措置は終了になりましたが、それでも電子データ保存の義務化対応に遅れが生じている企業が多数あるのが実情です。
そこで、2024年1月1日以降は、宥恕(ゆうじょ)措置のように期限を定めない新たな「猶予措置」が設けられています。
猶予措置では宥恕(ゆうじょ)措置とは異なり、電子取引データそのものは保管が必要です。
ただし、以下のいずれも条件を満たしてさえいれば、改ざん防止や検索機能といった満たすべき要件に沿った対応は不要です。
| ア.保存時に満たすべき要件を守って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請などは不要)
ロ.税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」およびその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じられる場合 |
電子帳簿保存法に対応するためのワークフローが整備されている場合などのケースでは、「所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合」という条件には当てはまらないはずです。
例えば経理関係書類は電子帳簿保存法に対応しているのに、見積書や注文書、契約書だけ紙に出力しての保存のみにするといったことは認められません。
また、猶予措置が認められるためには「税務署長が相当の理由がある」と認めることが必要です。誰でも望めば紙保管が認められるわけではありません。
宥恕(ゆうじょ)措置と猶予措置の違い
2023年12月31日をもって終了した宥恕(ゆうじょ)措置と、2024年1月から始まった「猶予措置」の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
| 宥恕措置 | 猶予措置 | |
| 期間 | ~2023年12月31日 | 無期限 |
| 内容 | ・電子取引データを保存していなくても良い
・税務調査などの際にデータの内容をプリントして提示または提出ができれば電子帳簿保存法の要件に従って保存できているとみなす |
・電子取引データの保存は必要(ダウンロードの求めに応じる必要がある)
・税務調査などの際に電子データおよびデータの内容をプリントして提示または提出ができれば電子帳簿保存法の要件に従って保存できているとみなす |
猶予措置では、宥恕(ゆうじょ)措置と違い、電子データの保存自体はおこなう必要があります。その根拠は「ダウンロードの求め」に応じる部分です。
宥恕措置では紙で保管している場合はダウンロードの求めに応じる必要はありませんでした。
しかし、猶予措置では税務調査でのダウンロードの求めに応じる必要があります。つまり、紙保存だけで済むのではなく、電子データとしても保存は必要ということです。
また、猶予措置が認められるには「税務署長が相当の理由があると認める場合」という規定をクリアする必要があります。誰でも単にデータで保管しておけば良いというものではありません。
例えばすでに電子帳簿保存法の要件を満たすためのワークフローが準備されているケースでは、一部のみ単に保管するだけで済ませるようなことはできません。
まとめ
2022年の電子帳簿保存法の改正によって、電子取引データを電子情報のままで保管することが義務づけられました。
2023年12月31日までは宥恕(ゆうじょ)措置によって条件付きで紙での保管が認められていましたが、宥恕措置も現在では終了しています。
代わりに2024年から「猶予措置」が開始されましたが、猶予措置では「税務調査でのダウンロードの求めに応じる必要がある」と表記されている通り、電子保存されていることが前提になります。猶予措置とはいえ、電子保存の義務を回避できるものではないということは知っておきましょう。
猶予期間に頼らずに電子保存の義務を遂行することで保管コストや紛失リスクが低減し、ビジネスの生産性向上につながります。
少しでも早くシステムやワークフローを整え、電子取引データの電子保存の仕組みをスタートさせましょう。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |