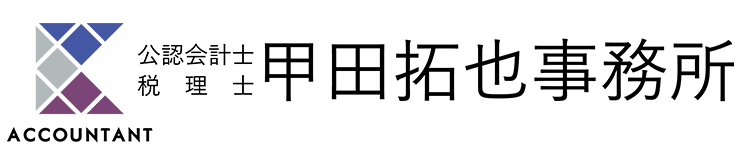定額減税の仕組みをわかりやすく解説!2024年6月から1人あたり4万円が減税になる!
投稿日: , 更新日: , 経費・勘定

2024年6月から月次減税事務などが開始される「定額減税」。税金負担が減る制度ということは分かっていても、詳細な内容は難しそうで調べていない方もいるのではないでしょうか?
本記事では物価上昇対策として始まった定額減税について、制度の概要や控除される金額などをわかりやすく解説します。
定額減税とは?制度の概要をわかりやすく解説

定額減税は、2024年6月から1年間実施される、1人につき4万円が減税される制度のことです。賃金の上昇が急激な物価上昇に追いついていない国民の金銭負担を緩和する目的があり、令和6年の所得税及び住民税から実施が決定されました。
制度の対象者
制度の対象になる人は所得税と住民税で以下のとおり異なります。
| 所得税 | ・所得税の納税義務者のなかで、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること など |
| 住民税 | ・住民税の納税義務者のなかで、前年2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること など ※均等割のみが課税される納税義務者は対象外 |
ご自身がいくら減税されるか知りたい場合は、扶養親族の条件を確認しておきましょう。
令和6年12月31日の現況で、以下の4つに当てはまる人が「扶養親族」に該当します。
- 配偶者以外の親族であること(6 親等以内の血族・3 親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が「48 万円以下」であること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
パートやアルバイトでも適用される?
正社員やフリーランスだけでなく、パート社員やアルバイトでも条件を満たせば定額減税がご本人に適用されます。なお、親や配偶者などに扶養されていないことが必要です。
アルバイト収入が103万円以下で親族に扶養されている場合は、扶養をしている人の方で、定額減税を受けるため、ご本人に影響はありません、
一般に、年収が100万円を超える場合には住民税がかかってくるため、扶養されていないのであれば、ご本人が住民税の定額減税を受けることは可能です。
アルバイト収入が103万円を超えて所得税が源泉徴収されていて、扶養に入っていないなら所得税の定額減税も本人が受けられます。年収103万円を超えていても、職場で源泉徴収がされていない場合は確定申告が必要です。
定額減税で控除される金額
定額減税で控除される金額は、納税者本人は所得税で3万円、住民税は1万円です。また、本人が扶養する家族1人につき所得税で3万円、住民税で1万円が追加控除されます。
「納税者本人・配偶者・子ども2人」の4人家族を例にすると、1人あたり所得税と住民税で4万円の控除になるため、4人家族では合計で16万円が控除という形で減税されます。
所得税と住民税が合計16万円減ることで、単純に手取りが16万円増えることになります。
定額減税の実施方法

定額減税の対象になるのは会社員だけではありません。個人事業主やフリーランスなどの「事業所得者」も対象です。
ただ、どの所得を得ているかによって、減税が行われるタイミングが異なる点に注意が必要です。
給与所得者
給与所得者の場合、2024年6月分の源泉徴収から家族1人あたり合計3万円が源泉徴収税額から減らされます。
2024年6月分で引ききれない場合は7月以降も継続して減税され、3万円×家族の人数分のすべてを減税しきるまで続きます。
住民税については2024年6月分の徴収がまずなくなります。そして、本来の年額から1人1万円を引いた金額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間であらためて徴収されます。
事業所得者
個人事業主など事業所得を得ている人の場合、予定納税があるか否かで所得税が減税されるタイミングが異なります。
予定納税がある場合には2024年7月の第一期から減税され、引ききれない場合には11月の第二期も継続して減税が続きます。一方、予定納税がない場合は翌年の確定申告のときに減税されます。
住民税については2024年6月分(第1期分)から家族1人につき1万円を徴収額から減税し、6月分(第1期分)で引ききれない場合には8月分(第2期分)以降の住民税から継続して差し引かれます。
定額減税を受けるのに特別な手続きは不要
一般的に、控除や減免、給付といった手続きをする際には市役所などでの手続きを要することが多いです。
しかし、定額減税に関しては特別な手続きは必要ありません。
給与所得者の場合、事務手続きは勤務先によって行われます。
個人事業主やフリーランスなどの自営業者の場合には、所得税は確定申告をすることで定額減税が行われます。確定申告は事業所得を得ている大半の自営業者が行うので、特に意識しなくても対象になります。住民税も普通徴収時に行われるので、特別な申し込みは不要です。
ただし、予定納税がある場合には手続きが必要です。7月に納める第1期分の予定納税額から本人分の定額減税分が控除されますが、同一生計配偶者や扶養親族は減税の対象に含まれません。
「同一生計配偶者」「扶養親族」の分も予定納税額から減税するには、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」が必要になります。
年金受給者については、公的年金等の支払者である厚生労働省や共済組合が手続きを行います。
減税しきれない分は「給付」も行われる
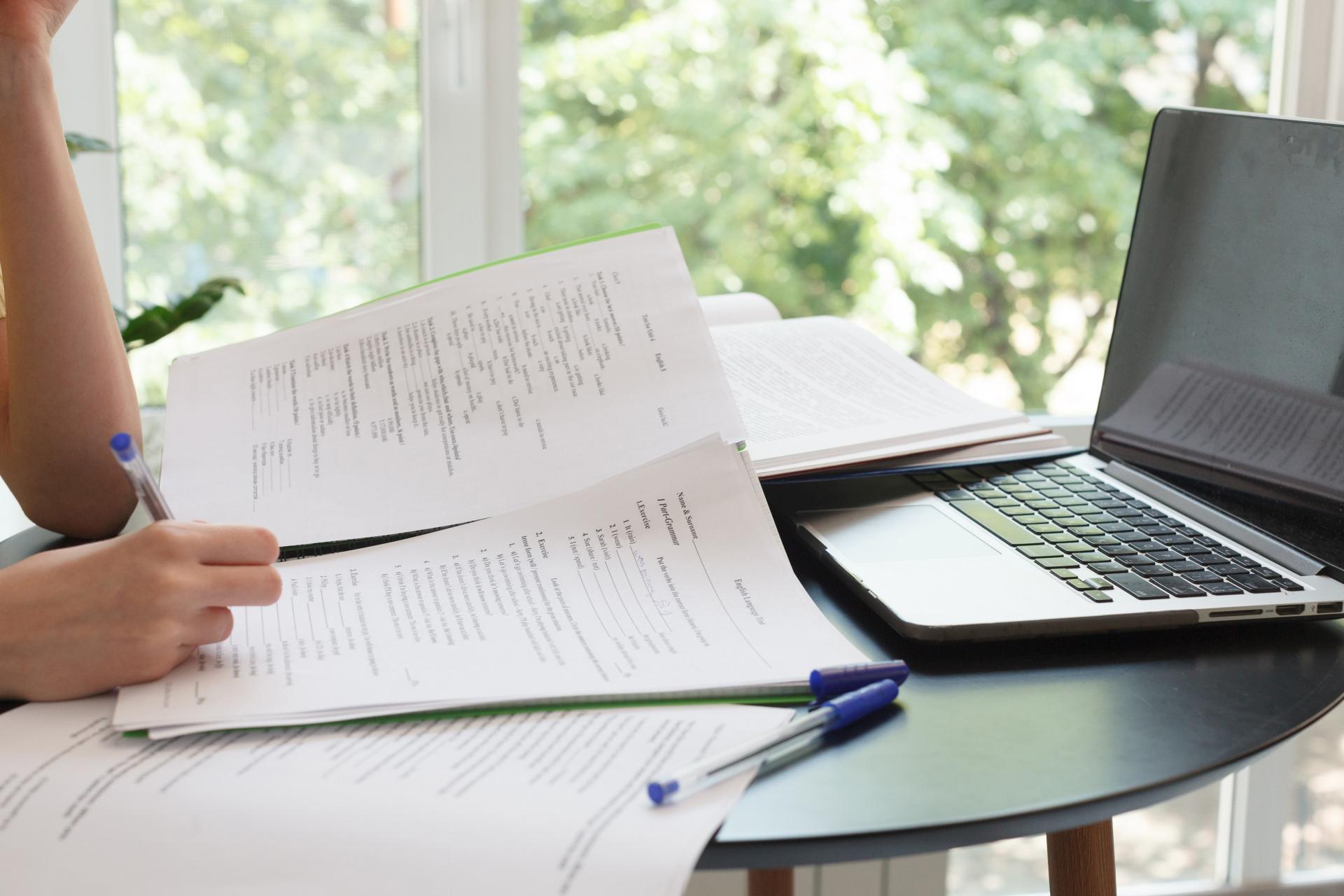
定額減税は扶養家族も含めて1人につき4万円(所得税と住民税の合計)が減税になる制度です。独身の方は1回で全額が控除されることが多いですが、子どもなどの扶養家族が多い場合には年間の納税額から全額を差し引けないこともあるかもしれません。
もちろん、単身者でも年収が低く納税額が少ない場合には、全額を引ききれないケースもあります。
全額を控除で使い切れない場合、政府は「給付」で補うと発表しています。給付は事務負担を軽減するために1万円単位で行われるため、仮に8,000円が控除できずに残っていた場合は1万円が給付されます、
定額減税の対象外の世帯には給付措置が行われる
本記事で紹介してきた定額減税は、納税額を減額する制度であり、そもそも納税していない世帯は制度の対象外です。
そのような住民税非課税世帯や住民税の均等割りのみ支払っているような、定額減税の恩恵を受けられない世帯には、代わりに給付金の支給が行われます。
例えば住民税非課税世帯の場合、2023年(令和5年)に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」として3万円の給付がすでに行われています。そこに7万円を新規に給付することで合計10万円の給付が行われます。
定額減税は住宅ローン控除に影響はない

住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて住宅を購入したり増改築したりした場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の 0.7 %」が、所得税や住民税から控除される制度のことです。
定額減税が行われると住宅ローン控除の控除額が減ってしまうと心配になる方もいるかもしれません。結論からいって、その心配は無用です。
定額減税が2026年12月までに引き切れない場合には1万円単位で給付が行われます。
また、ふるさと納税も同様です。ふるさと納税の控除寄付金の上限は定額減税を行う前の金額で計算すると決まっているため、定額減税を受けたからといって寄付できる金額が変わることはありません。
まとめ
定額減税では、納税者本人や配偶者・子どもなどの扶養親族1人につき、所得税と住民税で合計4万円の控除が受けられます。年間の合計所得金額が1,805万円以下など一定要件を満たす、大半の中間層は適用になります。本制度の対象外の低所得世帯もありますが、代わりに合計10万円の給付を受けることが可能です。
控除を受けた分だけ手取りが増えます。この機会に、生活費や旅行代金、資産運用など、お金の使い道を模索してみてはいかがでしょうか。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |