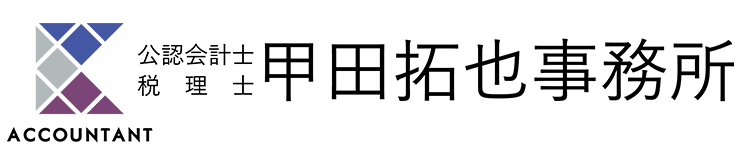法人の確定申告(決算申告)は自分だけでできる?税理士がいないときの申告の流れや作成手順とは
投稿日: , 更新日: , 年末調整・確定申告

法人には個人事業主と違って「確定申告」はありませんが、決算申告という手続きがあります。企業の事業年度ごとの損益や資産・負債・純資産などをまとめて必要書類を作成することで、個人の確定申告よりも複雑な手順が必要です。
ただ、小規模法人の場合は、税理士に依頼する以外に、自分で進めることもできます。
本記事では法人の確定申告にあたる「決算申告」を経営者が自分で進めるメリット・デメリットや、主な手続きの流れを紹介します。
法人の確定申告に当たる「法人決算」とは

法人決算は個人事業主の確定申告にあたる手続きのことで、法人が1年間の経営の通信簿である決算書を作成して申告と納税を行う手続きを指します。
決算では会社の資産・負債・純資産をまとめた貸借対照表や、損益計算書、その他には、株主資本等変動計算書、個別注記表などの所定の書類も作成することになります。
法人は事業年度終了の2ヶ月以内に法人税や消費税、法人住民税などを計算して税務署に申告・納税しなければいけません。申告期限が土日祝日などの場合は翌日が期限となります。
法人決算を税理士に依頼せずに自分で行うことはできる?

個人事業主が行う確定申告は、税理士に依頼する人のほかに自分で行う人も少なくありません。
一方の法人決算は税理士や会計士などに依頼することが一般的です。ただ、経営者が自分で決算申告をすることは可能で、法的にも何ら問題はありません。
ただ、中堅規模以上の企業の経営者の場合、膨大な取引を自社の人間だけでまとめて正確な決算を行うことは困難です。
ここでは、経営者が自分で法人決算ができるかどうかの判断基準を紹介します。
判断基準1:ひとり社長である
自分で法人決算を行う基準の1つめは、ひとり社長の法人であることです。
1人で決算業務をこなすには、取引量が少なめで内容がシンプルであることが求められます。ひとり社長なら仕事量も調整しやすく、決算期に通常業務をストップして決算業務に集中できる可能性があります。
判断基準2:売上規模が小さい
2つめは、会社の売上規模が小さいことです。
税理士という専門家を利用しないで決算をする場合、売上規模が小さくスモールビジネスであるほうが作業量が少ないため実現できる可能性があります。
決算をするには、日頃の経理業務を含めて簿記の知識を経営者自身が持つことが求められます。とはいえ、知識があったとしても膨大な取引量がある企業で、社長自らが業務の手を止めて確定申告をすることは難しくなります。
判断基準3:節税対策にはこだわらない
3つめは、節税対策にこだわりすぎないことです。
税理士は節税の知識を持ち合わせたプロフェッショナルであり、依頼することで最新の税制を踏まえたうえで節税ができるようなアドバイスをしてくれます。
法人経営者が自分で決算申告をする場合は税理士の手を借りることができないため、節税対策を取りにくくなります。
しっかりと節税をしていきたいと考えるなら、顧問料などのコストをかけても税理士に依頼したほうが良いでしょう。
法人決算を自分でやるメリット

法人決算を税理士に依頼せず、自分でおこなうメリットとして考えられるのは、主に以下の2つです。
税理士費用の削減になる
法人決算を自分でおこなうことで、税理士に支払う報酬を削減できるメリットがあります。
税理士事務所に決算申告業務を依頼した場合の報酬は税理士事務所ごとに異なるので一概にはいえないものの、一般的には決算申告業務のみの対応料金で15万円~25万円がかかるといわれています。
この税理士報酬を削減できることが、自社で決算申告をすることの大きなメリットの1つです。
決算の知識を経営に活かせる
決算を自社でおこなうことで、経営者自身や決算に携わった社員が経営の知識を身につけられるというメリットもあります。法人決算をするには税金や税制に関する専門知識が必要であり、法人決算をすることで自然と専門知識が身に付きます。
また、法人運営の通信簿である決算書類を作成することで財務状況や経営成績を把握でき、今後の経営方針を決める際にも決算での経験が活きるでしょう。
法人決算を自分でやるデメリット

法人決算を自分でおこなうことで税理士に顧問料や報酬を支払うことがなくなるというメリットがありますが、一方でデメリットも多くなります。
ここでは、法人決算を経営者自身が自分ですることのデメリットを見ていきましょう。
専門的な知識が必要で確定申告より難しい
法人決算は個人の確定申告よりも手続きが複雑で難易度が高く、簿記の専門知識がないと自分だけで完結するのは難しいとされています。
専門知識がないと決算書の記載内容をミスしてしまうことも考えられます。ミスの修正に貴重な時間や人件費をかけることで、せっかくの「税理士費用を削減できる」というメリットが薄まる可能性があります。
経営に使える時間が減少する
決算や会計の専門家に依頼せずに自分(自社)で決算書類を作成する場合、不慣れなぶんだけどうしても時間がかかります。不明点があれば調べ直し、ミスが見つかれば訂正することも必要です。
結果的に経営者自身の貴重な時間が決算業務に奪われることになり、営業や実務がおろそかになることで本業の業績が悪くなる可能性があります。
節約できた税理士への報酬以上の金額を本業で失うのは本末転倒です。
税務署の調査の対応に困ることになる
自分だけで決算申告をした場合、税務署が来たときの対応にも苦慮することになります。
自分で決算申告をするとどうしてもミスや認識の間違いが発生し、税務調査がおこなわれたときに担当者から鋭く質問される可能性があります。
税理士事務所を利用していれば税務署とのやり取りや対応も一任できますが、自分で決算をした分は自分で対応しなければいけません。
税務署からの指摘に対して納得できる回答ができないと追徴課税になり、かえって損になる可能性もあるでしょう。
法人決算の主な流れ・作成手順

ここからは、法人決算を進めるうえで知っておきたい、主な流れと書類の作成手順について解説します。
毎日の取引の記帳
法人が決算をするには、毎日の取引の内容を正確に記録する必要があります。取引による収入や支出、購入した商品や販売したサービス、顧客とのやり取りを帳簿に記入することで、決算での会計書類が迅速に行えるようになります。
帳票の整理
取引の記帳が終わったあとは、領収書や請求書などの帳票を整理する必要があります。これらを整理しておくことで決算書類や税務申告書などを作成する際に必要な情報を把握しやすくなるでしょう。
資産・負債の実査
決算書類を作成するにあたっては、会社にある資産と負債の実査が必要です。実査することで会社の資産と負債を正確に把握することができ、貸借対照表などの作成に役立ちます。
具体的には口座残高や債務の状況、財務諸表の現状を調べて、資産と負債の評価を行うことになります。
試算表の作成
決算をおこなう年度分の記帳などが全て完了したら、その記帳が正しく行われているかを確かめるための「試算表」を作成しましょう。試算表は仕訳や勘定記入の正確性を検証するための書類で1つの取引を2つの側面(借方・貸方)に分けて整理・記録したものです。
借方と貸方の金額合計はかならず一致するものであり、一致しない場合は記帳内容にミスがあったということになります。
試算表の作成には簿記の専門知識が必要ですが、会計ソフトを使うことで自動生成することも可能です。
決算整理仕訳
試算表を作成したあとは、決算整理仕訳をおこないます。
決算整理は決算のときに必要になる作業で、今期と来期をまたぐ取引などを修正する作業を指します。支払いが済んでいないもの、これから代金を受け取るものといった、入金・支払いが来期になる取引を確認して帳簿を修正することになります。
【決算整理仕訳で整理する勘定項目の例】
|
また、固定資産の減価償却費の計上や、棚卸資産の整理なども決算整理仕訳のタイミングで行うことになります。
税金の計算
これまで進めてきた手続きをもとに、法人税や法人住民税などの計算を行います。
決算書類の作成
決算整理仕訳と税金の計算が終了したあと、いよいよ決算書の作成に入ります。
法人決算で提出する書類の種類と特徴をまとめると以下のとおりです。
| 決算書類の名称 | 特徴 |
| 貸借対照表 | 決算日現在の資産・負債・純資産を表す書類 |
| 損益計算書 | 収益と費用をまとめ、1年間の利益を表す書類 |
| 事業報告書 | 事業年度ごとの会社の事業内容を報告する書類 |
| 個別注記表 | 各決算書類の注記事項をまとめた書類 |
| 株主資本等変動計算書 | 1年間を通じた株主資本の変動を表す書類 |
| 計算書類に係る附属明細書 | 貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書などの補足事項を表す書類 |
| 事業報告に係る附属明細書 | 事業報告を補足する書類 |
取締役会・株主総会の承認
決算書類を全て完成させたあとは、取締役会や株主総会での承認を受けることも必要です。
会社法では株式総会等への提出が定められているため、作成した決算書は株主総会に提出して承認を受けなければいけません。
株式会社では事業年度の終了後一定期間の時期に「定時株主総会」を招集することが定款で規定されており、定時株主総会で決算書の内容を報告して承認を得ることになります。
株主総会で承認を得ることで決算書類は「確定した決算」となり、決議に基づいて法人税の申告ができます。
税金の申告と納税
承認を得た決算書の内容で法人税申告書を作成し、決算書を税務署などに提出し、確定した税金を納めます。
法人税と消費税は所轄の税務署に納税しますが、法人事業税と法人住民税は地方税であるため都道府県税務書などに提出します。税金の種類ごとに申告先が異なる点には要注意です。
なお、決算の申告と納期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月後です。
決算書の保管
決算で使用した貸借対照表や損益計算書は、原則として税法上で7年、会社法では10年の保存が義務付けられています。
保存すべき書類の種類を確認したうえ、必要な期間にわたって間違いなく保管できるようにしましょう。
まとめ
法人経営者が自分で法人決算をすることは可能で、法的にも問題ありません。ただ、必ずしも自分で決算申告をすることが最適解ではないことに注意が必要です。
法人経営者が自分で法人決算を進めることにはメリットもありますが、決算が終わるまで事業運営ができなくなったり、節税がしにくくなったりするデメリットがあります。
顧問料や報酬を支払ったとしても、節税したうえで経営者が決算業務をする時間をフルに業務に充てたほうが結果的に得になるケースも少なくありません。
今回紹介した「自分で法人決算する際の流れ」を参考にしつつも、本当に自分で決算申告をするかは慎重に検討しましょう。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |