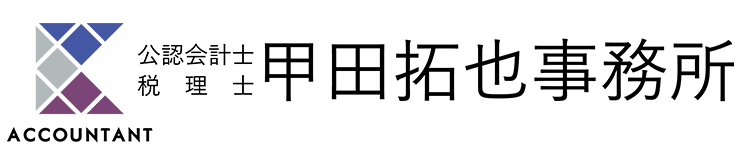定額減税の対象者は誰?制度の概要や控除額の計算方法をわかりやすく解説
投稿日: , 更新日: , 経費・勘定

2024年6月支給分給与から所得税と住民税の控除がスタートした「定額減税」。物価上昇への対策として政府が決定した制度で、納税者の手取りが増えることから注目が集まっています。
ただ、誰が対象者になるのか分からず「自分は定額減税の対象者なの?」と不安に感じている方もいるでしょう。
本記事では定額減税の対象者になる方の条件と、控除される内容やタイミングについてご紹介します。
定額減税は家族1人につき4万円が減額される制度

定額減税は、要件を満たす家族1人につき4万円が控除されるという形で減税される制度です。
昨今は急激な物価上昇によって企業の賃金アップが追いつかない状況が散見されており、国民負担を軽減するため、政府は税収の一部を国民に還元する政策として2024年6月から順次実施していく策を決定しました。
ほかにも日本政府はさまざまな物価高施策を打ち出していますが、なかでも定額減税は個人の可処分所得の増加が見込まれることから注目されています。
「定額」「定率」の違いとは
今回の定額減税は、文字通り、制度の対象者であれば年収に関係なく誰でも同じ金額が控除されます。似たような言葉に「定率」がありますが、両者には以下のような違いがあります。
- 定額:一定の金額
- 定率:一定の割合
定率の場合、例えば「所得税の10%が減税」のような制度になるでしょう。定率では所得税を多く納めている高額所得者のほうが恩恵を受けられます。
今回の定額減税では年収300万円でも年収1,000万円でも同じ金額が控除されるため、低所得者ほど減税効果が相対的に大きくなります。
定額減税で減額になる金額
定額減税の対象になるのは「所得税」「住民税」の2つです。減税される額は2つの税制で以下のように異なります。
【所得税】
- 納税者本人:3万円
- 同一生計の配偶者または扶養親族:1人あたり3万円
【住民税】
- 納税者本人:1万円
- 同一生計の配偶者または扶養親族:1人あたり1万円
所得税と住民税を合わせると、家族1人につき4万円が減税になります。
なお、令和6年中に新たに子どもが生まれたり、扶養親族が増えたりした場合、所得税の減税の対象には含まれますが、住民税は対象外です。住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに計算されていることによります。
定額減税の対象者になる人の条件

定額減税の対象になるのは「納税者本人」「同一生計配偶者」「扶養親族」の3種類です。ただし、誰でも制度が適用されるわけではなく、一定以上の収入を得ていたり特定の要件を満たさなかったりする場合には対象者にはなれません。
ここでは納税者・同一生計配偶者、扶養親族の支給要件を見てみましょう。
納税者本人が定額減税の対象者になる条件
定額減税を受けるには、納税者本人が要件を満たす必要があります。
| 所得税 | ・所得税の納税義務者のなかで、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること ほか |
| 住民税 | ・住民税の納税義務者のなかで、前年2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること ほか ※均等割のみが課税される納税義務者は対象外 |
定額減税は低所得者から中間層の救済策であり、年収2,000万円を超える高所得者層は対象外になっています。
「同一生計配偶者」の条件
納税者が定額減税の要件を満たしている場合、減税額に同一生計配偶者の分が加算されます。夫婦2人住まいで妻が扶養されている場合、所得税6万円、住民税2万円の計8万円が減税になります。
同一生計配偶者の要件は以下のとおりです。
- 令和6年12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者であること
- 青色申告書の事業専従者または白色申告者の事業専従者ではない
- 年間の合計所得が48万円以下であること
「扶養親族」の条件
家族のなかに配偶者以外に扶養親族がいる場合も、本人と同額の控除額が加算されます。夫婦2人(うち1人は被扶養者)と子ども1人の家庭の場合、要件を満たせば所得税9万円、住民税3万円の計12万円が控除の対象になります。
- 令和6年12月31日の現況で、納税者と生計を一にする扶養親族(6 親等以内の血族・3 親等内の姻族)であること
- 青色申告書の事業専従者または白色申告者の事業専従者ではない
- 年間の合計所得が48万円以下であること
定額減税を受けられる対象者は「給与所得者」「個人事業主」「年金受給者」など
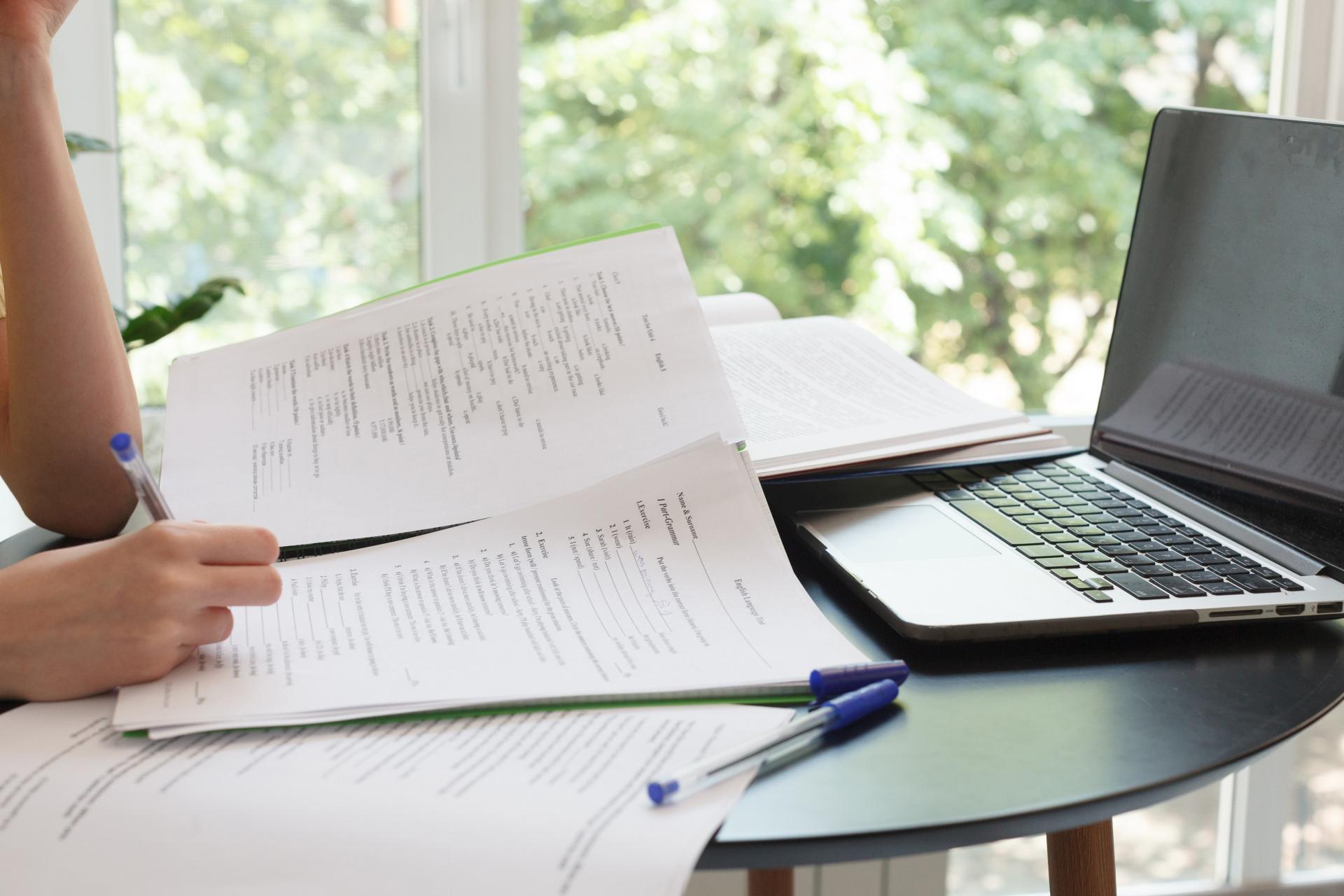
定額減税を受けられるのは、源泉徴収や確定申告、普通徴収などで所得税・住民税を納めている納税者です。現金の給付ではないので、納税していない人は扶養家族としてカウントされない限りは制度の対象には含まれません。
制度の対象になる納税者としては「給与所得者(会社員・公務員など)」「個人事業主」「年金受給者」の3つがあります。
給与所得者の定額減税の流れ
給与所得者の場合、令和6年6月1日以降の最初の給与支給分の源泉徴収税額から、「3万円×制度対象の家族人数」が控除されます。6月支給分給与で全額控除できない場合は7月以降に順次控除が続き、それでも控除しきれない場合は年末調整で控除されます。
個人住民税については、6月分が徴収されません。令和6年度分の住民税の「所得割額」から減税額を差し引いて残った金額を11等分して、令和6年7月~令和7年5月で毎月特別徴収されることになります。
個人事業主の定額減税の流れ
個人事業主の場合、予定納税の有無で控除のタイミングが異なる点に注意が必要です。
予定納税がある場合には2024年7月の第一期分から本人分の減税額が控除され、引ききれない場合には11月の第二期分に渡り継続して減税が続きます。それでも控除額が残るなら確定申告での精算となります。配偶者や扶養親族の分を控除するのは確定申告のときです。
一方、予定納税がない場合は、翌年の確定申告のときにまとめて減税されます。
年金受給者の定額減税の流れ
年金受給者の場合、所得税は令和6年6月に支給される年金の源泉徴収税額から控除されます。
住民税は令和6年10月に年金から特別徴収される金額から順次控除され、引ききれない分は令和7年2月までの年金受け取りの際に控除されていきます。
アルバイトが定額減税の対象者になるか・ならないかは収入や扶養で異なる

アルバイトとして働いて生計を立てている「フリーター」でも、定額減税の対象者に含まれる可能性はあります。
まず、アルバイト収入が年103万円以下で家族の扶養に入っている場合、扶養している方ご本人の定額減税の対象になります。
一方、年収が100万円を超えていれば所得税がかからなくても住民税の所得割を納めることになります。誰にも扶養されていないなら、住民税の控除は受けることができます。
まとめ
定額減税の対象者には「給与所得者」「個人事業主」「年金受給者」などがいますが、納税者本人の年収が高すぎたり日本に居住していなかったりすると対象に含まれないことがあります。
ご自身やご家族が対象になるか条件をよく調べてみて、控除が正しく受けられているかを源泉徴収票などで確認してみましょう。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |