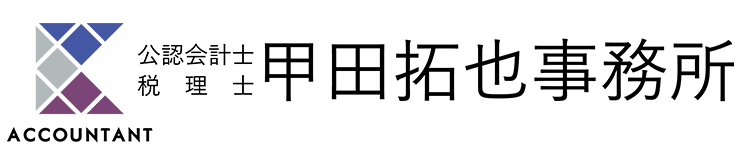定額減税で年金受給者はどうなる?1人あたり4万円が減税される制度の概要と年金受給者が受け取れるのかを解説
投稿日: , 更新日: , 経費・勘定

2024年6月以降支給分から、1人あたり所得税と住民税で4万円が控除される「定額減税」の制度がスタートしました。年金受給者で「年金しか収入がない人も対象になるの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では定額減税制度の概要と、年金受給者が制度の恩恵を受けられるかについて解説します。
定額減税はデフレ脱却を目的に所得税と住民税が1人当たり計4万円の減税になる制度

「定額減税」とは、賃金の上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度住民税の減額が行われる制度のことです。
本制度では、納税者および、配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の計4万円が減税されます。
制度の対象になる人は所得税と住民税で以下のとおり異なります。
| 所得税 | ・所得税の納税義務者のなかで、2024年分の合計所得金額が「1,805万円」以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること ほか |
| 住民税 | ・住民税の納税義務者のなかで、前年2023年の合計所得金額が「1,805万円以下」(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人
・日本国内の居住者であること ほか ※均等割のみが課税される納税義務者は対象外 |
注意点として。本制度の適用を受けるには、日本国内に居住していることが条件です。
定額減税の人数に数えられるための条件
定額減税の対象になるのは「納税者本人」「配偶者」「扶養親族」です。このうち配偶者と扶養親族に関しては、対象になるための条件が決まっています。
「配偶者」としてカウントされるための条件は以下のとおりです。
- 「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された、国内居住している源泉控除対象配偶者
- 合計所得金額の見積額が 48 万円以下であること
一方、「扶養親族」に数えられるための条件は以下のとおりです。
- 配偶者以外の親族であること(6 親等以内の血族・3 親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が「48 万円以下」であること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
定額減税が適用されたかどうかの確認方法
定額減税された金額については、毎年12月に送付される「源泉徴収票」で確認が可能です。源泉徴収票の「摘要欄」に所得税から実際に減税された金額」と「減税しきれなかった金額」の記載があります。
年金受給者の方で源泉徴収が行われていれば交付されるので、気になる方は該当の源泉徴収票が発行された後に確認してみましょう。
一方、主に6月と12月に交付される「年金振込通知書」には減税後の所得税額のみが記載されているので、減税された金額はわかりません。
定額減税は年金受給者も受給の対象になる

令和6年の所得税と令和6年度の住民税から本人を含む家族1人につき4万円が減税される定額減税制度。減税された分だけ手取りが増えるため、ご自身が対象になるか気になる方もいるでしょう。
定額減税は会社勤めの給与所得者、事業所得を得ている個人事業主だけでなく、すでにリタイアして年金生活を送っている年金受給者の方も対象です。
ただし、定額減税は富裕層を対象にすべきではないとして、給与所得で年収2,000万円、所得が1,805万円を超える人は控除を受けることができません。
減税の対象①所得税
所得税について源泉徴収を受けている国内居住者に関して、令和6年6月以降に支給される年金の源泉徴収税額から、受給者・配偶者・扶養親族1人につき3万円が控除されます。
控除しきれない金額は、令和6年12月支払までの年金の所得税源泉徴収において順次控除されます。
減税の対象②住民税
個人住民税に関しては、令和6年10月に年金から特別徴収される金額から、年金受給者1人と、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円が控除されます。
控除しきれない金額については、令和7年2月までの年金支払いで順次控除される仕組みです。
年金受給者の定額減税の実施方法

公的年金を受け取っている年金受給者に対して、定額減税を実施する方法は以下のとおりです。
年金受給者の所得税の定額減税の実施方法
公的年金の受給者かつ源泉徴収の対象者のもとには、すでに年金機構から「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付済みです。
控除対象になる配偶者や扶養親族を記載して返送すれば、その内容に基づいて同一生計配偶者と扶養人数が決定し、控除される金額が決まります。
その後は2024年6月1日以降支給分で、最初に受け取る公的年金の源泉徴収で所得税額から定額減税の控除額が差し引かれます。
年金受給者の住民税の定額減税の実施方法
公的年金の受給者の場合、2024年分の「定額控除前の住民税額」をもとに2024年10月分の税金額が計算され、10月分の年金から定額減税分が控除されます。
住民税に関しては所得税と違い、納税者が提出するべき書類はありません。
年金に関する定額減税を受けるための手続きはない
年金受給者の方が定額減税を受けるために、市役所などに出向いて手続きすることは特にありません。
令和6年分の「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していれば、記載内容に基づいて定額減税の計算が行われます。
ただし、「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等届出書」を提出していない場合、本人分のみの定額減税が行われることになるため注意が必要です。
また、老齢年金以外にほかの年金や所得があるなど定額減税額の精算が必要な場合は手続きが必要です。複数の年金や給与所得を受け取っているような場合、それぞれ源泉徴収される所得税から減税が行われます。
重複して定額減税を受けた場合には、確定申告で最終的に年間所得税額と定額減税額を確定させることになります。
定額減税額が年金の源泉徴収より高い場合には「調整給付」になる

年金の源泉徴収額が少なく、定額減税の金額のほうが高い世帯もあるでしょう。控除しきれなかった金額については「調整給付」にて減税額との差額は精算されることになります。
給付は事務負担を軽減するために1万円単位で行われます。仮に5,000円が控除できずに残っていた場合は1万円が給付されます。
まとめ
定額減税制度は源泉領収で所得税や住民税を納めている年金受給者も対象に含まれます。本人と一定要件を満たした配偶者、扶養親族1人につき所得税は3万円、住民税は1万円の控除を受けることが可能です。
控除された金額分だけ手取りが増えるため、孫へのプレゼントや夫婦での旅行など、この機会にお金の使い道を考えてみてはいかがでしょうか?
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |