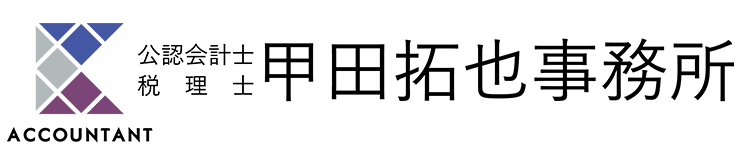役員退職金の功績倍率が「3倍」なのはなぜ?退職金が不当に高額といわれないためのポイント
投稿日: , 更新日: , 経営

中小企業の多くで経営者の高齢化が進んでおり、世代交代が企業の大きなテーマになりつつあります。
社長や役員が退職する際に支払われる「役員退職金」は会社の資産を大きく減らして株価を下げられることから事業承継の手段として魅力的ですが、不当に高額と判断されて否認される可能性もあります。
否認される可能性を下げるためには、通例として用いられる功績倍率などの計算式を利用して適正金額を探ることが必要です。
本記事では、役員退職金の功績倍率が3倍なのはなぜか、不当に高額と言われないためのポイントなどについて解説します。
役員退職金とは

役員退職金は文字通り、社長など会社の役員が退職した場合に、在任期間中の対価を後払いとして支給する役員給与のことです。
役員退職金(税務上では「役員退職給与」)は、法人税法上、事業遂行上の経費として「損金」に算入できるとされています。
ただし、税法上で「不当に高額な部分」とされた役員報酬については役員賞与となり、損金に算入することができません。
以下の3つのポイントに照らして、その退職する役員に対する給与として認められる相当額を超える場合に、その金額が「不当に高額」と判断される可能性があります。
・法人の業務に従事した期間
・その退職の事情
・同業類似会社の役員退職給与の支給状況など
なかでももっとも重視されるといわれているのが「同業類似会社の役員退職給与の支給状況」です。
役員退職金の計算方法は法的な決まりはないが、実務では一定の計算式を利用して決められる

役員退職金の金額について、明確に規定する税法上の決まりや通達はありません。役員退職金は、法人に支払い余力さえあれば、いくら支給しても問題はありません。
ただし、適正であると認められなかった部分に関しては損金とは認められないことが、法人税法施行令第70条で明記されています。
| 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額 |
上記をみると、「いくら以上が損金と認められないか」という具体的な金額は明示されていません。
実務では以下の計算式を利用して適正な退職金額を算出することが多いです。
▼役員退職金を算出する際の計算式の例
| 最終の役員報酬月額×役員勤務年数×功績倍率 |
この計算式に用いられる「功績倍率」は、実務では「3倍」と計算されるのが通例です。
役員退職金の功績倍率は3倍が妥当といわれるのはなぜ?

前述の計算式では、「最終月の役員報酬×勤務年数」に3をかけ合わせた数字が、妥当な退職金額ということになります。
ではなぜ、3倍が妥当とされているのでしょうか?
それは、昭和40~50年代にあったいくつかの裁判において、3倍が妥当という判例が出たことが、今も生かされているからです。
昭和55年に東京地裁が下した判決において、当時の全上場会社1,603社の実態調査の結果から算出された功績倍率の平均が以下のとおりであったと示されました。
・社長3.0倍
・専務2.4倍
・常務2.2倍
・平取締役1.8倍
・監査役1.6倍
上記の判例を受け、会社の代表者である社長が退職する際に支給される退職金の計算式に組み込む功績倍率は、「3倍」を目安にすることが多いのです。
役員退職金が不当に高額と判断されないためのポイント

役員退職金(役員退職給与)の適正額は、「法人の業務に従事した期間」「その退職の事情」「同業類似会社の役員退職給与の支給状況など」に照らして判断されることになります。
なかでも税務上とくに重視されるのは「同業類似会社の役員退職給与の支給状況など」です。
実務上では他社の退職金の支給状況を会社が把握するのは困難であることから、3倍の功績倍率が採用されるケースが多くなります。
ただ、裁判のなかには「1.06倍」「1.18倍」といった低倍率が適正と判断されたケースもあります。つまり、裁判に進んでしまうと平均功績倍率が2倍を下回る数値と認定されてしまうリスクがあるのです。
2倍以下の倍率では損金として否認されるリスクが増大するため、功績倍率を3倍に設定するためにも、税務調査の時点で調査員を納得させ、裁判まで進めないことは重要といえるでしょう。
調査官を納得させるには、国で示した功績倍率に沿って役員退職金規定を設定し、役員報酬を計画的に算出しておくことが大切です。
同業類似会社の選定方法
役員退職金の妥当性を調査する際に同業類似会社を設定する場合、以下のようなことが考慮されます。
| 業種:「日本標準産業分類の大分類」及び「国税庁が定める業種分類整理番号上定める中分類」における業種が同一か否か
地域:立地条件や経済事情に共通性があるか 事業規模:資本金額や売上金額、総資産価額、所得金額などに類似性があるか 退任状況:退任事由は「普通退職」「死亡退職」のいずれなのか、退任者の役職は常勤か非常勤かなど 判定時期:役員退職給与を支給した事業年度を含めて、その前後の事業年度中に役員退職給与の支払いがある会社か |
役員退職金で知っておきたい注意ポイント

ここからは、役員退職金を設定するに当たって知っておきたい注意点を解説します。
- 形式的な退職だけで役員退職金とは認められない
- 功績倍率3倍以上の退職金額にするには具体的な理由が必要
形式的な退職だけで役員退職金とは認められない
会社の役員が形式的に退職した場合では、役員退職金と認められない場合があります。
例えば役員退職金を受け取ったあとも、引き続き会社経営の重要な地位にいる場合には、役員退職金は認められません。
ただ、引き続き会社に在籍する場合でも、業務分掌の変更によって役員としての地位や職務内容が激変して「実質的に退職したと同様」とみなされるときは、役員退職金として認められます。
▼役員退職金として認められる分掌変更の一例
|
功績倍率3倍以上の退職金額にするには具体的な理由が必要
支給功績倍率の目安は3倍までとお伝えしてきましたが、法的に3倍が上限と決まったわけではありません。理由によっては、3倍以上の倍率を設定しても全額を損金算入できる可能性はあります。
実際、3倍以下の功績倍率でも否認されている判例はあります。高額な役員退職金額を支給する場合、退職金としての妥当性や否認される税務リスクまで考慮しておくことが大切です。
まとめ
役員退職金の金額を算定する際には、「最終の役員報酬月額×役員勤務年数×功績倍率」という計算式が用いられ、功績倍率は3倍が通例です。
「3倍」という倍率に法的な決まりはありませんが、過去の判例が今までずっと利用されています。不当に高額な退職金と判断された部分は損金算入ができないため、基本的には過去の判例に従った金額で退職金を算定することになるでしょう。
裁判まで進んでしまうと否認リスクが上がるため、税務調査の調査官を納得させる金額設定にすることが推奨されます。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |