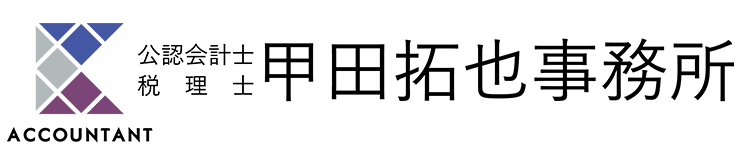法人税の申告期限は3ヶ月に延長可能!延長できる理由と手続き方法を解説
投稿日: , 更新日: , 年末調整・確定申告

法人の場合、決算のあとに必ず「法人税の申告と納税」の手続きを行う必要があります。法人の申告・納税期限は決算日を基準に決められ、遅れると本来は延滞税や無申告加算税などの対象になります。
ただし、どうしても期限内の申告が難しい場合には、期限延長の手続きが可能です。
本記事では法人税の申告期限の原則と延長できる理由、延長する際の手続き方法について解説します。
法人税の申告期限は原則として「決算日の翌日から2ヶ月以内」

個人事業主の場合は所得税の申告期限が「毎年2月16日から3月15日」と決められていますが、法人税については一律に定められているわけではありません。
会社の事業年度の開始と終了の日にちは会社の定款で定めます。一般的には3月31日や12月31日が多いですが、ほかの日にちを選択することも可能です。
そして法人税の申告期限は、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月後」が原則です。
決算日の2ヶ月後が、土曜・日曜・祝日など税務署の閉庁日である場合は、その次の開庁日が申告期限として設定されます。
法人が申告・納税するべき税金

法人が申告・納税すべき税金としては、主に以下のようなものがあります。
- 法人税
- 法人地方税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
それぞれの特徴や税率について解説します。
法人税
法人税は、法人の事業活動で得た利益に対して課税される「国税」です。「資本金1億円以下の法人など」に分類される場合、年800万円以下の部分は15%(適用除外事業者は19%)、年800万円超の部分は年23.2%と定められています。上記以外の普通法人は年23.2%の税金が課されます。
法人地方税
法人税を課税標準とし、計算する国税です。所轄の税務署を通じて国に納めますが、最終的には地方自治体に分配されます。
法人住民税
法人住民税は、事業所のある地方自治体に対して法人が納める「地方税」です。法人住民税は「法人税割」「均等割」の2つの基準で構成されており、それぞれの算出金額の合計が課税されます。
法人事業税
法人事業税は、法人が事業を行う際に利用した行政サービスに対し、維持などにかかる経費の一部を負担するための「地方税」です。法人の種類のほか、資本金額、年間所得などで税率が変動し、算出された税金は都道府県に納付します。
消費税
消費税は「課税事業者」の事業主が納めるべき税金です。国内における資産の譲渡や貸付け、役務の提供に対して課されます。
国の消費税と地方自治体の地方消費税として構成されており、税務署を通じて納めることになります。
期限まで申告できなかった場合は罰則が加算される

法人税の申告と納税期限は決算日の2ヶ月後が原則で、それに遅れた場合にはさまざまな罰則が科される可能性があります。
申告が遅くなるほど罰則は重くなるので、申告期限に間に合わせるような納税が必要です。
申告遅れの原因によっては申告期限の延長も可能であるため、期限に間に合わない場合は延長も視野に入れつつ、できるだけ早く納税の準備を進めることが必要です。
期限後に自己申告した場合
期限後に自己申告する「期限後申告」は、後述する「期限後に税務署から申告される場合」と比較して、軽い罰則で済みます。
ただし、申告する前に税務調査が入って所得金額や税額を確定する通知が届いたときには期限後申告はできません。
期限までに納税していないことを税務署に指摘された場合
税務署に指摘されるまで確定申告をせずに放置した場合、税務調査が入る可能性があります。
税務調査では税務署が「所得金額」「納めるべき税金額」の通知を行い、納税者は通知に従って納税する義務があります。税務署の指示に従わないと督促が行われ、それでも納税しないと財産の差し押さえなどの処分が下される可能性もあります。
税務調査が入ったあとでは罰則が重くなるため注意が必要です。
法人税の申告期限は特例によって3ヶ月以内に延長も可能

前述のとおり法人税の申告期限は「決算日の翌日から2ヶ月以内」であり、通常であれば期限を過ぎると延滞税や無申告加算税といった罰則の対象になります。
ただし、一定の理由によって決算申告ができない場合、最大で決算日の翌日から3ヶ月以内まで申告期限の延長が可能です。
とはいえ、どんな法人でも申告期限を延長できるわけではありません。延長するには、以下のような理由付けが必要になります。
決算が確定しない場合
法人の株主総会の招集は事業年度終了後3ヶ月以内と決まっています。
事業年度の終了から2ヶ月目以降3ヶ月目以内に株式総会を行う法人の場合、通常の申告期限まで株主総会が開かれず、法人税の金額が確定しないケースがあります。
株主総会の開催日程の問題で法人税の申告が期限通りにできない場合には「申告期限の延長の特例」の申請をすることで1ヶ月の期限延長が可能です。
災害などやむを得ない理由がある場合
地震や台風、津波など、やむを得ない自然災害によって申告・納税に間に合わない場合、国税庁長官が地域や期限を指定したうえで申告・納税期限の延長を実施します。指定された地域に該当する法人の場合、特に申請や手続きをせずとも申告・納税の期限が延長されます。
国税庁長官の決定した延長期限にも間に合わないときや、指定された地域以外の法人でも災害で法人税の申告が難しい場合には、状況次第でさらなる延長の手続きをすることも可能です。
法人税の申告期限の延長の申請方法

法人税の申告期限の延長を決定した場合、延長のための正式な手続きをおこなうことになります。
法人税の申告期限の延長に必要な手続きは主に以下のとおりです。
- 申請書を提出する
- 見込納付を行う
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
申請書を提出する
法人税の申告期限の延長には「申告期限の延長の特例の申請書」の提出が必要です。書式は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
申請書に必要事項を記載したあと、法人がある地域を所轄する税務署に持参、または送付をします。
延長を申請する理由には「会社の定款で、決算日から3ヶ月以内に株主総会を開催するため」など、延長せざるを得ない理由を正確に記載することが重要です。
見込納付を行う
法人税の申告期限の延長は可能ですが、納税期限は延長することができません。よって、申告期限を延長したからといって納税しないと利子税が加算されることになるため注意が必要です。
利子税を回避するためには「見込納付」という手続きが必要です。納付するべき税金を概算して納付し、申告期限後に差額を精算する方法を指します。
多めの金額を納税した場合は差額について、「更生の請求」を行うことで、あとから返還されます。
【注意】法人税の申告期限は延長できても納税延長はできない

災害が起きてどうにも申告・納税することができず、国税庁の長官から「申告・納税の猶予」が発表された場合、申告だけでなく納税期限も延長される可能性があります。
一方、株主総会の時期が事業終了年度の3ヶ月以内であることなど、会社側の都合で法人税の申告ができずに延長するケースでは、納税期限までは延長されません。
本来の申告期限までに納税できない場合、延長期間に応じた利子税が課されます。
実務では本来の申告期限に「見込納付」を行うことになりますが、見込納付した金額が本来の納税額に満たなければ、満たない分については利子税が課されるため注意が必要です。
| 【利子税の計算式】
本則:7.3% 特例:0.9%(令和7年分) |
まとめ
法人税の申告期限は原則として「決算日の翌日から2ヶ月以内」と決められており、期限までに納税できないと「延滞税」「無申告加算税」などが課されます。罰則の金額は延滞した期間が多いほど重くなり、自己申告ではなく税務署からの指摘ではさらに重くなるケースもあります。
自然災害や株主総会が法人税の申告期限までに終わらないなどの正当な理由があれば、法人税の申告期限の延長の特例を申請しましょう。
ただし、納税期限は延長できないため、申告期限を延長する場合には、法人税の納税期限に一度概算で「見込納付」を行い、払い過ぎた分は後日還付を受けることになります。
なお、法人税の申告期限の延長は事業年度の終了日までにおこなう必要があります。期限に遅れて申告できないと単なる申告遅れになってしまうため、事前に納税期限に間に合わないことがわかった時点で早いうちに申告延長の手続きをおこないましょう。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |