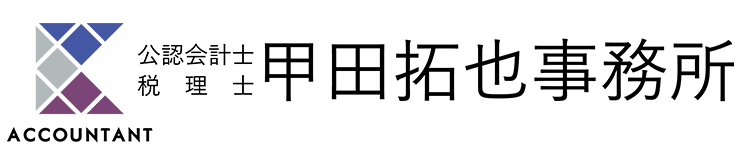法人税の申告期限は延長できる?手続きができる理由と注意点
投稿日: , 更新日: , 年末調整・確定申告

ƒ法人税の申告は原則として「決算日から2か月以内」に終わらせる必要があります。ただ、自然災害をはじめ、仕方なく申告期限を過ぎてしまう場合には、延長の手続きをすることも可能です。
本記事では法人税の納税期限の原則と納めるべき税金の種類、期限延長できる理由や注意点について解説します。
法人税の申告期限は原則「事業年度終了の翌日から2か月」

法人税の申告は毎年必ず訪れますが、その締め切りは法人ごとに異なります。
個人事業主の方が行う所得税の確定申告は毎年「2月16日から3月15日」までに終わらせるのが原則ですが、法人の場合は以下のとおりです。
| 原則、事業年度終了の翌日から2か月以内 |
例えば3月31日が決算日の場合、5月31日が法人税の申告と納税の期限ということになります。
税務署への申告書の提出・納税はもちろん期限厳守であり、申告と納税が遅れた場合は「延滞税」「無申告加算税」といったペナルティの支払いも必要になります。
法人が申告・納税するべき税金
法人が申告・納税すべき税金としては、主に以下のようなものがあります。
- 法人税
- 法人地方税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
それぞれの特徴や税率について解説します。
法人税
法人税は、法人の所得に課税される「国税」です。「資本金1億円以下の法人など」に分類される場合、年800万円以下の部分は15%(適用除外事業者は19%)、年800万円超の部分は年23.2%です。上記以外の普通法人は年23.2%の税金が課されます。
法人地方税
法人税を課税標準とし、計算する国税です。所轄の税務署を通じて国に納めますが、最終的には地方自治体に分配されます。
法人住民税
法人が地域の構成員であることについて課される「地方税」です。会社の事務所や事業所などを置いている都道府県と市町村に納めます。法人住民税は「法人税割」「均等割」の2つの基準で構成されており、それぞれの算出金額の合計が課税されます。
法人事業税
法人の事業活動に対して課税される「地方税」です。法人の種類や資本金額、年間所得などで税率が変動し、算出された税金は都道府県に納付します。
普通法人(資本金1億円以下・年間所得2,500万円以下)で2019年10月1日以後開始の場合、下記の区分の税率になるのが一般的です。
- 年間所得400万円以下の部分:年3.5%
- 年間所得400万円超800万円以下の部分:年5.3%
- 年間所得800万円超の部分:7%
消費税
消費税は法人の事業主だけでなく、個人事業主も含めた「課税事業者」の事業主が納めるべき税金です。国内における資産の譲渡及び貸付け、ならびに役務の提供に対して課されます。
国の消費税と地方自治体の地方消費税として構成されていますが、申告と納税は税務署を通じて納めることになります。
法人税と申告期限の延長とは

法人税の納税期限は決算日の翌日から2か月以内であり、その期限内に法人税の申告と納税を行うことになります。
しかし、何らかの理由で2か月以内の申告ができないケースがあるかもしれません。
その場合、「定時株主総会を事業年度終了後3ケ月以内に行う」と定めていれば、決算終了2か月以内に決算が確定しないという理由のもと、「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出できます。
延長の申請をしておくことで、法人税の申告期限を1か月延長することが可能です(連結法人・通算法人ではない普通法人の場合)。
法人税の申告期限を延長できる理由としては、主に以下の2つがあります。
災害などのやむを得ない事情があるとき
日本は地震大国であり、大地震やそれに伴う津波、または台風や土砂崩れなどが原因で、企業活動そのものができなくなる可能性もあります。
地震や風水害などどうしようもない自然災害を受けて決算申告ができない場合、国税通則法第11条による申告期限の延長が可能です。
実際には地域指定・対象者指定・個別指定の3つの延長方法があります。
| 条件 | 内容 | 申告などの延長後の期限 | |
| 地域指定 | 都道府県の全部または一部に被害の影響が出ている | 国税庁長官が地域と期日を告示
⇒納税者による申請は不要 |
国税庁長官が指定した日 |
| 対象者指定 | 被害により多くの納税者が、電子申告や特定の税目の申告などに対応できない | 国税庁長官が対象者の範囲と期日を告示
⇒納税者による申請は不要 |
国税庁長官が指定した日 |
| 個別指定 | 上記以外 | 納税者が所轄の税務署長に申請 | 税務署長が指定した日 |
会計法人からの監査を受けなければいけないとき
会計監査人の監査を受けなければならず、事業終了年度の2か月以内に決算が確定しない場合、法人税申告の期限延長が認められます。
延長できる期限は1か月で、事前に法人税申告書の提出期限の延長を所轄の税務署に申請する必要があります。
ただし、会見監査人の監査対象になるのは、「上場企業」や、「資本金5億円以上もしくは負債200億円以上の企業」と、大規模法人に限られます。
定款などに定めがあるとき
法人の定款などの定めにより、または特別な事情のため、本来の法人税の申告期限までに定時株主総会の開催ができないケースでも、申告期限の延長が可能です。
定時株主総会は決算に伴うものであり、決算の内容が定時株主総会で承認されないと決算の申告書を作成できません。
このような事情があるため、法人税の申告期限のあとに定時株主総会がある法人については法人税の申告期限を延長させることが可能です。
法人税の申告期限を延長するときの注意点

法人税の申告期限を延長できるのは、これまで解説してきたとおりです。ただし、延長できるのはあくまでも「申告期限」であり、「納税期限」は延長することはありません。
決算から3か月以内に株主総会がある法人では事業年度終了から2か月以内に決算が確定せず、申告することができませんが、見込みで納税することになります。
ここでは法人税の申告期限の延長期限に関する注意点として、「利子税」「延滞税」の存在について解説します。
国税には利子税がかかる
定款などの定めがある申告の期限の延長をすると、国税の場合は無申告加算税や延滞税といったペナルティは発生しません。その代わりに発生するのが「利子税」です。
| 【利子税の計算式】
本則:7.3% 特例:0.9%(令和7年分) |
地方税は延滞金がかかる
地方税でも、定款の定めによる申告期限の延長は可能です。しかし申告期限を延長しても納税の期限は延長されず、法定納期限の翌日から「延滞税」が発生します。
| 【延滞税の税率】
令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合 1.納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合 2.納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 引用元:国税庁|延滞税の計算方法 |
まとめ
法人税の申告・納税期限は原則として「事業年度終了の翌日から2か月以内」です。ただ、自然災害や会計監査人による監査、定時株主総会がおこなわれるタイミングが申告期限より後だったなどの理由があれば、申告期限を延長することは可能です。
延長するには決算日までに税務署に延長の申請をする必要があるため、延長か必要か否かをできるだけ早く判断しましょう。
あくまでも延長できるのは「申告期限」のみで納税期限は延長できない点には注意が必要です。
監修者
 |
甲田拓也 (公認会計士税理士甲田拓也事務所 代表)
早稲田大学卒業後、PwCグローバルファームや個人会計事務所を経て現事務所を設立。節税、資金繰り、IPO・マーケ支援を行うプロ会計士として活動。YouTubeでも情報発信中! |