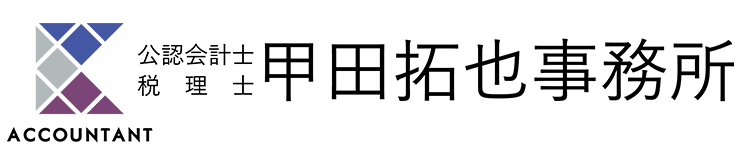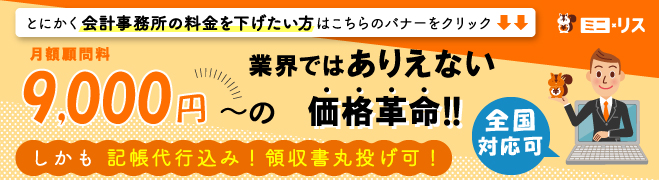家賃支援給付金 これをやったら不正受給!
投稿日: , 更新日: , コロナ関連

皆様こんにちは。
私どもが6月11日にアップしたブログ「持続化給付金を不正受給すると… Σ(゚Д゚)」には大変多くの反響をいただきました。持続化給付金に関しては安易に不正受給を進めるコンサル業者の存在も問題視される中、経済産業省は不正受給に関する調査を開始し、先日ついに不正受給による逮捕者も出ました。
一方で家賃支援給付金については当初から不正受給対策が図られ、多くの提出書類が必要とされているうえ審査にも時間がかかる旨アナウンスされています。しかしながら家賃支援給付金についても不正受給の手口がないわけではなく、また留意しないと意図せざる不正受給に該当してしまうケースも考えられます。
そこで今回は家賃支援給付金の申請にあたって、「これをやったら不正受給!」をテーマに取り上げます。
こんなケースでは要注意
自宅兼事務所におけるケース
自宅兼事務所における家賃も給付対象にはなりますが、給付対象となるのはそのうち事務所部分のみです。では事務所にかかる割合は何を使うのかというと、原則として確定申告の際に必要経費算入額の算出に用いた割合を用います。個人事業主の場合、青色申告された方であれば青色申告決算書の3ページ目、白色申告の方であれば収支内訳書の2ページ目に「地代家賃の内訳」の項目で計算されていることと思いますので、ここで用いた割合を使います。
今回の家賃支援給付金の申請にあたっては、個人事業主で青色申告をされた方の場合、確定申告書については青色申告決算書の1・2ページ目の提出が求められているのみで、家賃の按分割合がわかる3ページ目の提出は求められていません。つまり、按分割合を確定申告における必要経費算入額の算出に用いた割合より多い割合で申請する余地があるということになります。後に調査が入ったとき、確定申告の際に用いた按分割合よりも多い割合で適当に按分して(もしくは按分すらせず自宅部分も含めて全額)申請したとなると、不正を疑われるリスクが高まることには注意が必要です。
転貸におけるケース
借主が借りている土地や建物の一部を第三者に又貸しをした場合(これを転貸といいます)、転貸部分については今回の給付対象とはなりません。
万一、転貸部分も含めて給付申請をしてしまうと、これも場合によっては不正を疑われることになるので注意が必要です。
親族への家賃支払におけるケース
親族への家賃支払は基本的には給付の対象となりません。具体的には自らが所有する物件、もしくは父母、妻もしくは夫、子供が所有する物件に対する家賃支払は対象外ということになります。
一方で二親等までの親族(つまり祖父母や孫など)が所有する物件に対する家賃支払であれば給付の対象となります。
ここで問題になるのはこうした二親等までの親族間における家賃支払を偽装してしまうケースです。
今回の家賃支援給付金の申請に契約書や家賃支払実績がわかる通帳の写しが必要なのは前回のブログで書いた通りです。しかし契約書がない場合や、家賃が現金で支払われていて、なおかつ領収書も発行されないような場合には、これらに代えて「賃貸借契約等証明書」や「支払実績証明書」を用意すればよいことになっています。
親族間の借主と貸主が結託して賃貸借契約等証明書や支払実績証明書にそれぞれ自署をし、家賃支払額を実際よりも水増しして申請し、後日折半するといった不正も考えられます。万一こうした不正が発覚した場合にはかなり悪質なものと認定されることになるでしょう。
不正受給をするとどうなる?
不正受給への対応は基本的には持続化給付金の場合と同様です。
家賃支援給付金事務局は、提出された基本情報などについて確認を行い、不審な点がみられる場合などには、関係書類の提出要請、事情聴取、立入検査などの調査をおこなうことがあるとしています。
この結果、家賃支援給付金事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件にあてはまらないことなどが判明した場合には、申請者に対して不給付決定をおこない、不正受給が疑われる場合には、以下の対応を行うとしています。
| ♠ 不正受給した給付金全額に、年率3%で算定した延滞金、さらにこれらの合計額に20%を加えた額の支払命令 ♠ 申請者の法人名・屋号・雅号などの公表 ♠ 内容次第では不正受給した申請者を告訴または告発 |

まとめ
故意に不正受給を行った場合に重いペナルティが課されることは言うまでもありませんが、今回の家賃支援給付金で留意すべきは意図せざる不正受給です。今回取り上げたケース以外にも申請においてトラップとなるケースはあり得ます。持続化給付金と比べて複雑な今回の家賃支援給付金の申請にあたっては、可能であれば身近な専門家のアドバイスも聞きながら、慎重に行われることをお勧めいたします。
【ブログの内容に関するお問合せについて】
最近私どものブログに大変多くの反響をいただいております。弊所ではブログに関するお問合せについてもメールやお電話での無料相談を承っておりますが、現在こちらについては顧問契約前提のお客様に限定させていただいております。なにとぞご了承のほどお願い申し上げます。
▼▼▼お読みくださりありがとうございました。よろしければクリックをお願いいたします。
![]()
![]()